これまで何度か孫子に関わるブログを書いている。
孫子は戦略に関わる著書の中で最も有名なものと言えるが、その内容はかなり広範であり、ビジネスに応用できる教えも多い。孫子の名言の1つに「百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」があり、勝つことよりも戦わない方が賢明だというのは、中小企業にとって重要な示唆である。
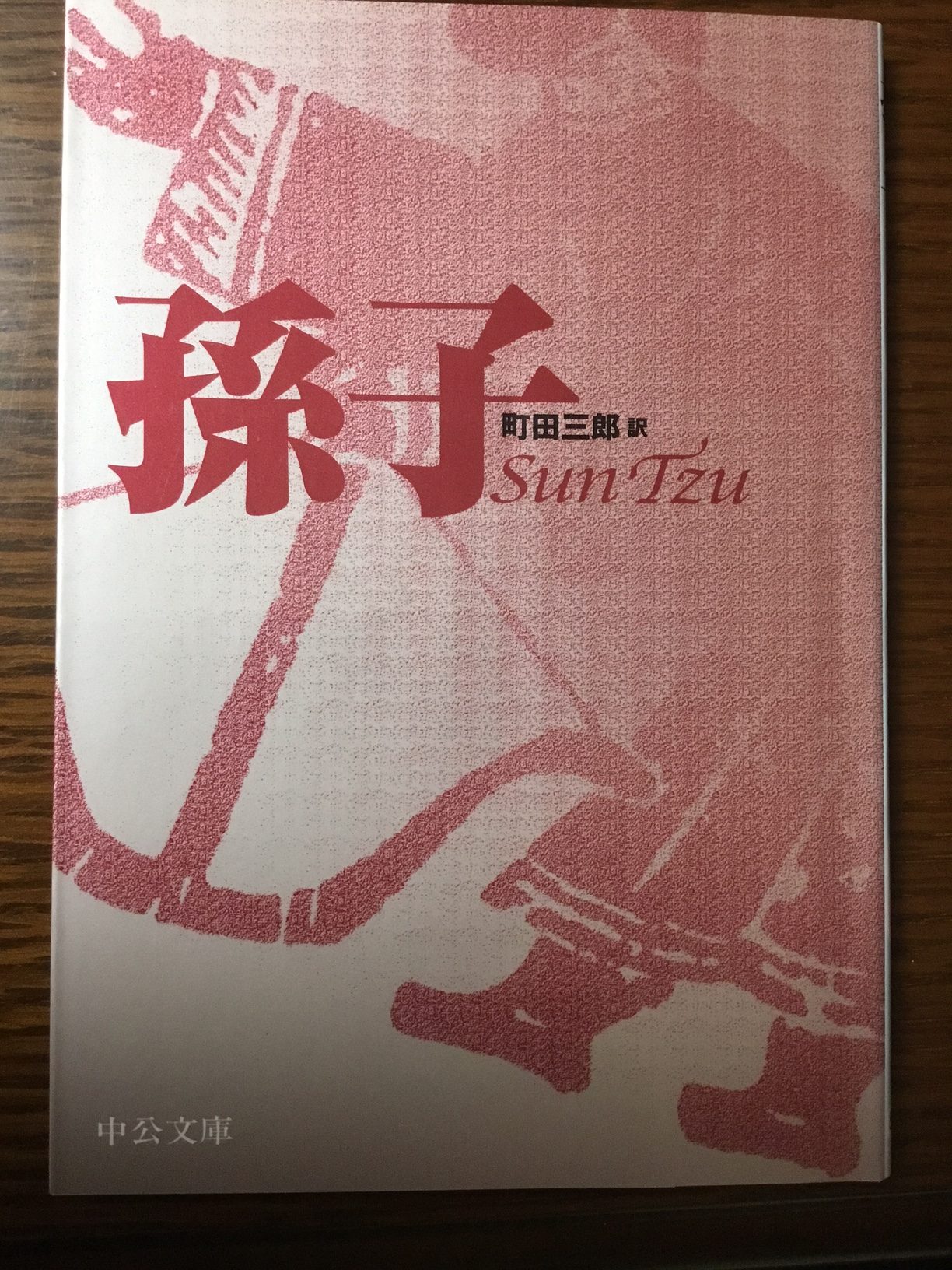
■戦わなければならない場合はどうなのか?
戦いは回避すべきかもしれないが、そうは言ってもどうしても戦わなければならない場合もある。その時に大切なことは何か?
孫子では、戦う場合の基本原則として「短期決戦」、そして「不敗」を説いている。つまり争いが長期化しないこと、そして負けないことである。不敗とは勝っても負けてもいない状態であり、もちろん勝つことがべターであるが、勝てるかどうかは相手次第という「他力」の要素が入り込む。「自力」で防御に徹して不敗を守るのが可とも言える。
■勝つための決め手は?
相手に勝つための要素として、①戦力の差、②精神力の差、③情報・技術の差の3つがあるとされている。
戦力は、ビジネスの世界では経営資源と換言できるが、相対的に人材・資金・設備等が豊富な方がライバル企業よりも優位に立てるというのは自明だ。この格差が大きいと勝敗を逆転させることはかなり難しい。ただし、特定の領域(時間・場所・分野など)に限定することができるのであれば、相対的な戦力の優位性は確保しやすくなる。
精神力は、士気をいかに高めるかが重要になる。組織内での危機感の共有、あるいは良い意味での成功体験の積み重ねにより「勢い」をつけることで大きな力を得ることができる。
情報は相手よりも早く、多く収集できれば当然優位に立てるし、独自の技術やノウハウを保有することで戦いを優位に進めやすくなる。しかしながら、経済活動でデジタル化が進展する中で、情報や技術の優位性を維持することは難しくなっている。

■人材育成とは組織の「勢い」をつけること
スポーツでは前評判が高くなかったチームが躍進するという場面をよく目にする。たとえば、高校野球でノーシードの公立高校が優勝候補の強豪校に勝ったり、あるいはサッカー天皇杯でJ2・J3のチームがJ1の強豪チームに勝って、その勢いで上位に進出する(さらには優勝する)ということがしばしば起こる。これは、10回戦って1回勝てるかどうかという相手に勝ったことで勢いに乗ったのである。強かったから勝ったというよりも、勝ったことで「もしかして俺たちは強いかもしれない」という自信を持つことで強くなったというものだ。
「勝ちぐせ」をつけるためには、小さな成功体験を少しずつ積み重ねることが必要だ。成功体験とはポジティブなフィードバックを得ることでもあるが、顧客からの感謝、上司からのほめ言葉、良好な人事評価などは自信の根源になり得る。さらに「あいつにできるなら、おれにだってできるはず」という勢いの連鎖が組織に広がる効果もある。その意味で上司の仕事は、より多くの部下に「手柄を立てさせること」であり、これが人材育成の近道だろう。

